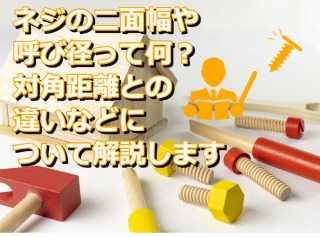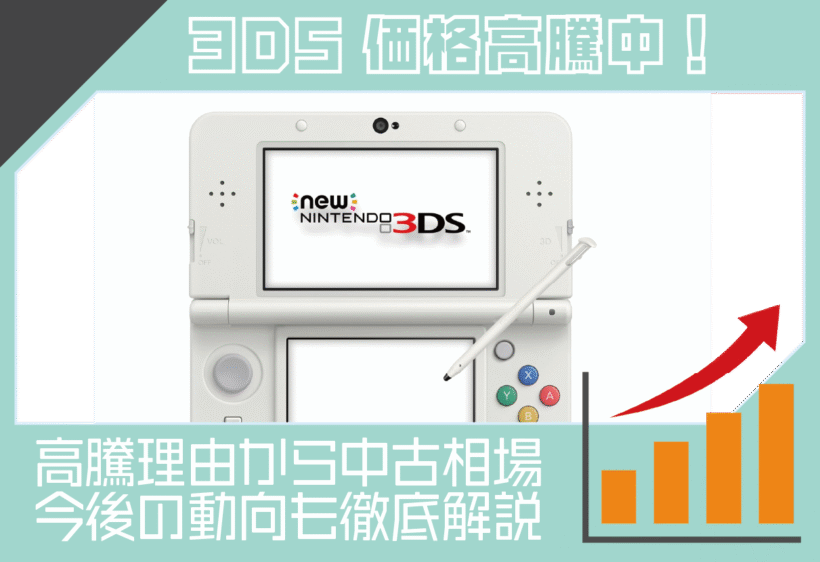【購入前に知っておきたい】電動工具のDIY用モデルとプロ用モデルの違いについて解説します
目次

ハンズクラフト西日本最大級の工具専門リユースショップです。
ハンズクラフト【工具専門】西日本最大級の総合リユースショップです。
当店は創業20年以上、工具・家電を中心に扱うリユース専門館です。お買取りした中古品を綺麗にメンテナンスして新たな価値を吹き込み、福岡・北九州地域を中心に沖縄や山口・広島まで17店舗を展開中です。各記事は工具専門のスタッフや、工具・家電の修理専門部門が監修・執筆しています。
「なぜ同じメーカーなのに価格がこんなに違うの?」
電動工具売り場で、そんな疑問を感じたことはありませんか?
実は、主要メーカーの多くが「DIY用」と「プロ用」で明確に製品を分けています。
見た目は似ていても、中身は全く別物。この違いを知らずに購入すると、「すぐ壊れた」「パワー不足だった」と後悔することに……。
逆に言えば、違いさえ理解すれば、用途に合った最適な一台が見つかります。
そこでこの記事では、プロモデルとDIYモデルの違いを徹底解説します。
購入前に知っておきたいポイントもお伝えするので、買い替えや新規購入を検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
DIY用モデルとプロ用モデルの違いについて

電動工具には、DIY用モデルとプロ用モデルの2種類が存在します。
実は両者は、利用シーンに合わせて根本的に異なる設計がされています。
DIY用途であっても、作業内容によってはプロ用モデルが必要になるケースも。
それぞれの違いや特徴を理解することで、購入後の後悔を確実に減らせます。目的に合った工具選びには欠かせない知識です。
作りが根本的に違う!4つの重要ポイント
DIY用モデルとプロ用モデルは、設計段階から違いがあります。具体的な違いは以下の4点です。
- 長時間使用・ハードな扱いへの耐久性
- 精密作業に対応できる精度
- 求められるパワーの違い
- 騒音への配慮レベル
プロ用モデルの特徴
仕事として電動工具を毎日使うプロにとって、耐久性は生命線です。
長時間の連続使用やハードな扱いに耐えられなければ、仕事になりません。
プロ用モデルはブラシレスモーターやメタルギアを採用し、連続運転対策が施されています。
全体的に高い耐久性を誇り、長年使用しても壊れにくい設計です。
また、高精度な部品を使用しているため、作業の仕上がりも安定します。
騒音面でも静音化設計が進んでおり、特にHiKOKIの「WH18DDL2」などは優れた静音性を実現しています。
DIY用モデルの特徴
一方、DIYでの使用は軽作業がほとんど。過酷な条件下での使用は少ないため、軽量・コスト抑制設計となっています。
連続使用は非推奨ですが、休日の作業には十分な性能です。
近年では18Vリチウムイオンバッテリー搭載の高性能機も増えており、DIY用でも十分なパワーを発揮できるケースが多くなっています。
つまり、利用シーンに合わせた最適化設計がされているのです。
メーカー別の見分け方(マキタとHiKOKIの場合)
国内トップシェアを誇るマキタとHiKOKI(旧・日立)では、型番とシリーズでDIY用とプロ用を区別しています。
【型番による見分け方】
マキタ:
- DIY用 → Mから始まる型番(例:「MT」シリーズ)
- プロ用 → TやDから始まる型番
HiKOKI:
- DIY用 → Fから始まる型番(例:「F」シリーズ)
- プロ用 → Wから始まる型番(例:WH18DDL2)
型番を見るだけで、どちらのモデルか判別できます。
【カラーについての注意点】
以前はカラーでの区別が一般的でしたが、近年では多色展開が進み、カラーのみでの判別は困難になっています。
- マキタ:DIY向け「Mシリーズ」は赤・黒系が多いですが、プロ用でも5色展開(青・黒・白・ピンク・オリーブなど)が一般的
- HiKOKI:DIY向けに白・黒などもあり、世代によって異なります。
確実な判断方法は、シリーズ名・型番、または販売ルート(ホームセンター限定モデルなど)で確認することです。
※一部の製品(例:マキタの「18Vシリーズ」など)は、プロ・DIYの境界が曖昧な機種も存在します。メーカーによっては明確に2分類されていないケースもあります。
価格の違い
DIY用とプロ用では、使用部品や設計の違いから価格に大きな差があります。
以下に例を挙げるので、価格の違いを見てみましょう。
●マキタの価格比較(標準小売価格)
●HiKOKIの価格比較(標準小売価格)
- DIY用「FWH18DGL (2LEGK)」:28,700円
- プロ用「WH18DC(2XPZ)」:75,600円
(2025年10月現在各社公式サイトの価格を参考)
数千円の違いではなく、プロ用が約2倍もしくはそれ以上高いことがわかります。
軽作業中心なら、DIY用を選ぶことで高いコストパフォーマンスを実現できます。
逆にハードな使用が想定される場合は、プロ用を選ぶことで耐久性と精度の高さから長期的な満足度が得られるでしょう。
プロ用モデルとDIY用モデル、どっちを選ぶべき?

価格も性能も大きく異なる両モデル。
迷ったときは、「どんな作業に使うのか」を基準に選びましょう。
電動工具のプロ用モデルを買い揃えるべき人の特徴
プロ用モデルが最適なのは、プロまたはプロ並みの作業をこなす人です。
プロで1日8時間・週40時間ほど使用する場合、年間で計算すると膨大な稼働時間です。
しかし休日のみのDIYでも、以下に当てはまるならプロ用を検討すべきでしょう。
【プロ用がおすすめなケース】
- ハードな作業(厚い木材の切断、金属加工など)
- 高い精度が要求される作業
- 連続稼働時間が長い
- 音をなるべく抑えたい環境
連続稼働しなくても、負荷の高い作業は可動部の消耗を早めます。頻繁な買い替えは、結果的に出費増に繋がることも。
また、プロ用モデルは高精度な部品で構成されているため、騒音が少ないのも大きな特徴です。
電動工具のDIYモデルを買い揃えるべき人の特徴
DIY用モデルが最適なのは、軽作業中心で負荷の低い作業を行う人です。
どんなにDIY好きでも、毎日何時間も作業できる人は少数派でしょう。
休日に作業時間が増えても、時間が長いだけならバッテリーを買い足すか、容量の大きいものを購入すれば解決します。
【DIY用がおすすめなケース】
- 精度はそこまで必要ない(または違いがわからない)
- 稼働は休日がメイン
- 今は電動工具を持っていない
- まずは手軽に始めたい
2024年以降、DIY用モデルでも18Vリチウムイオンバッテリー搭載の高性能機が増えています。
以前と比べて出力・耐久性ともに向上しており、DIY用でも十分なパワーを発揮できるケースが多くなっています。
まずはDIY用モデルから始めて、徐々にステップアップ。
物足りなくなったときに初めて、プロ用を検討することをおすすめします。
まとめ
電動工具のプロ用モデルとDIYモデルは、性能・価格・設計思想など、あらゆる面で差別化されています。
購入前にこの違いを知っておくだけで、失敗を大幅に減らせます。
・軽作業中心・・・DIY用でコスパ良く(近年は高性能化が進行中)
・ハードな作業や高精度が必要・・・プロ用で長期的満足度を
判別方法としては、カラーではなく型番やシリーズ、販売ルートで確認することをおすすめします。
あなたの用途に合った一台を見つけて、快適な作業ライフを手に入れましょう。
工具選びに役立つ知識は、まだまだあります。ぜひ他の関連記事もチェックして、理想の工具を見つけてみてください!
関連記事
不要な工具は
ハンズクラフトへ
工具専門で20年
買取価格に自信があります!
大切な工具だからこそ、工具専門店にお任せください。