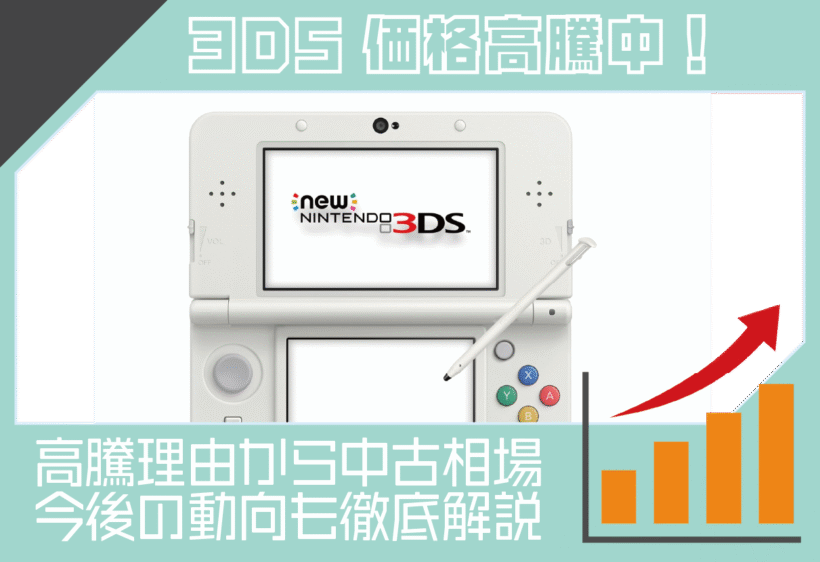テールゲートリフター義務化の基本から対策まで徹底解説します
目次

ハンズクラフト西日本最大級の工具専門リユースショップです。
ハンズクラフト【工具専門】西日本最大級の総合リユースショップです。
当店は創業20年以上、工具・家電を中心に扱うリユース専門館です。お買取りした中古品を綺麗にメンテナンスして新たな価値を吹き込み、福岡・北九州地域を中心に沖縄や山口・広島まで17店舗を展開中です。各記事は工具専門のスタッフや、工具・家電の修理専門部門が監修・執筆しています。
2024年2月1日よりテールゲートリフター義務化が施行されました。
特別教育を受けずに操作させた場合、事業者には罰則が科せられる可能性があります。
この義務化は、電動・油圧式リフターを使用するすべての事業者が対象です。
本記事では、テールゲートリフター義務化の具体的な内容から特別教育の受講方法、未対応時のリスクまで詳しく解説していきます。
テールゲートリフターとは何か
 テールゲートリフターは、現代の物流業界に欠かせない重要な設備です。
テールゲートリフターは、現代の物流業界に欠かせない重要な設備です。
まずは基本的な仕組みと、なぜ多くの企業で導入が進んでいるのかを確認していきましょう。
トラックに搭載される昇降設備
テールゲートリフターは、トラックの荷台後部に取り付けられる荷物の昇降装置です。
重量物や大型荷物の積み下ろし作業において、人力では対応困難な場面で威力を発揮します。
電動や油圧の力を利用して荷台と地面の間を荷物が移動できるため、作業者の身体的負担を大幅に軽減できます。
とくに重量のある荷物を扱う配送業務では、なくてはならない装置といえるでしょう。
導入が加速する理由
近年の導入拡大には明確な背景があります。
EC市場の急成長により配送量が激増し、同時に運送業界では深刻な人手不足が続いています。
こうした状況下で企業は業務効率化を急務としており、テールゲートリフターは「少ない人員で安全かつ効率的に荷役作業を行う」という課題解決の有効な手段として注目されているんです。
労働災害のリスク低減効果も期待され、導入企業は年々増加しています。
特別教育の義務化とは
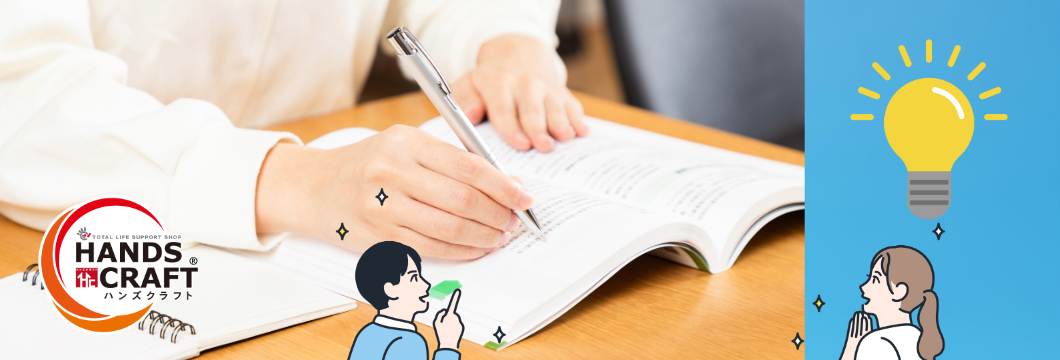
労働安全衛生規則の改正により、2024年2月1日からテールゲートリフターを使用した荷役作業に特別教育が義務化されました。
ここでは、義務化の詳細な内容と対象範囲について説明していきます。
義務化により変わること
特別教育の義務化により、事業者は作業従事者全員に対して決められたカリキュラムの教育を実施する必要があります。
教育を受けていない従業員にテールゲートリフターを操作させることは法律違反となり、事業者が責任を問われます。
この制度は、不適切な取り扱いによる墜落、転落、転倒などの労働災害が発生していることを受けて導入されました。
適切な知識と技能を身につけることで、事故リスクを大幅に減らすことが目的です。
対象となる設備と業種
義務化の対象は電動・油圧式のテールゲートリフターに限定されます。
手動で操作する簡易的な装置は対象外です。
業種による制限はなく、テールゲートリフターを使用して荷物の積み下ろし作業を行うすべての事業所が対象となります。
運送業だけでなく、製造業や小売業なども含まれるため、幅広い業界で対応が必要です。
施行時期と対応の緊急性
制度は既に施行されており、現在も対応していない事業所は直ちに特別教育の実施が求められます。
猶予期間は設けられていないため、該当する事業者は速やかな対応が不可欠です。
未対応時のリスクと対策

特別教育を実施しない場合、法的な処罰だけでなくさまざまなリスクが発生します。
適切な対応方法とあわせて、具体的なリスクを確認しておきましょう。
法的処罰と企業への影響
特別教育を行わなかった場合、罰則が存在します。
労働安全衛生法違反として、事業者には6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があるんですね。
さらに深刻なのは、教育不足による事故が発生した場合の影響です。
企業の社会的信用失墜、損害賠償責任、業務停止処分など、経営に致命的な打撃を与える可能性があります。
法的リスクを避けるためにも、確実な対応が必要といえるでしょう。
保有車両の確認方法
対応の第一歩として、自社車両の状況把握から始めましょう。
保有するトラックにテールゲートリフターが搭載されているか、それが電動・油圧式であるかを確認します。
次に、実際の使用状況を調査します。
どの作業でリフターを使用し、誰が操作しているかを明確にすることで、特別教育が必要な従業員を特定できます。
この調査結果をもとに、教育計画を立案しましょう。
設備導入を検討する場合
現在テールゲートリフターを搭載していない企業でも、手作業の限界を感じている場合は導入を検討する価値があります。
新車購入時に標準装備として選択するか、既存車両への後付け設置が可能です。
初期投資は必要ですが、長期的には作業効率向上、人件費削減、安全性確保といったメリットが期待できます。
導入と同時に特別教育も実施することで、法令遵守と業務改善を同時に実現できるでしょう。
特別教育の具体的な内容について

特別教育について「どのような内容なのか」「費用はいくらかかるのか」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
ここからは、教育制度の詳細と実施方法について詳しく解説していきます。
特別教育制度の基本
特別教育は、労働安全衛生法に基づいて危険性の高い業務に従事する際に必要な専門教育です。
事業者が従業員に対して実施する義務があり、外部機関への委託または自社での実施が可能となっています。
技能講習との違いは、特別教育が事業者責任で実施する教育であるのに対し、技能講習は国家資格として登録機関でのみ実施される点です。
特別教育では修了証の交付または実施記録の保管が求められます。
教育対象者の範囲
テールゲートリフターの操作の業務(荷役作業を伴うものに限る)に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が事業者に義務付けられています。
対象となるのは、リフターの昇降板を直接操作して荷物の積み下ろしを行う作業に従事するすべての労働者です。
雇用形態による区別はなく、正社員、契約社員、パート、アルバイトを問わず、作業に関わるすべての従業員が教育を受ける必要があります。
カリキュラムと所要時間
特別教育の内容は、学科教育4時間、実技教育2時間の合計6時間で構成されています。
■学科教育(4時間)の内容
・テールゲートリフターの基本知識(1時間)
・構造、操作方法、点検整備に関する知識(2時間)
・荷役作業の安全確保と関係法令(1時間)
■実技教育(2時間)の内容
・実際の操作訓練
・点検作業の実習
費用と実施方法
外部の教育機関に委託する場合、1人あたり1万円から1万5000円程度が一般的な費用相場です。
また、2024年1月31日以前に6ヵ月以上の実務経験を有する方が対象の一部免除コースも用意されており、この場合は4.5時間の短縮カリキュラムとなります。
自社実施の場合は外部委託費用は不要ですが、社内に適切な指導者を育成する必要があります。
材準備や指導者の時間確保などを考慮して、最適な実施方法を選択しましょう。
まとめ
今回は、テールゲートリフター義務化の内容や対象条件、特別教育の受講方法について解説しました。
2024年2月1日から施行されているこの義務化は、電動・油圧式リフターを使用するすべての事業者が対象となります。
未対応の場合は罰則が科せられるリスクがあるため、ぜひ本記事を参考にして、未対応の方は早急に特別教育の実施を進めてください。
適切な対応により、法令遵守と職場の安全性向上を実現しましょう。
関連記事
不要な工具は
ハンズクラフトへ
工具専門で20年
買取価格に自信があります!
大切な工具だからこそ、工具専門店にお任せください。